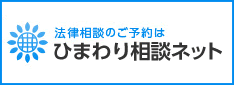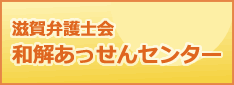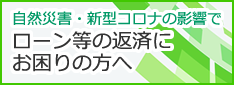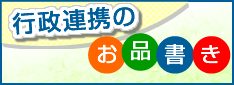会長声明・決議
会長声明・決議
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」案に対する会長声明
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」案(以下、「均等法改正案」という。)は、現在開会中の第164国会に内閣から提出され、4月28日参議院本会議で、「5年後の見直し」規定を付加して修正議決し、同日衆議院に送付された。
日弁連では、既に昨年6月16日付で均等法改正について詳細な意見書を発表しているほか、本年4月5日、具体的法案に関して、「間接差別」・「仕事と生活の調和」・「賃金」という特に重要な3点に絞って日弁連会長声明を発した。その後の参議院厚生労働委員会の審議の中でも、やはり、これらの点が議論の中心となっており、その問題性がますます明らかとなってきている。
1.「間接差別」とは、性別以外の理由による措置が、実質的には性別による差別に等しい効果をもたらすものをいう。昨年6月22日厚生労働省から発表された学識経験者らによる「男女雇用均等政策研究会報告書」では、間接差別法理導入の目的を「一方の性に対して不利益を与える不必要かつ不合理な障壁を取り除き実質的な機会の均等を確保することにある」と述べている。 しかし、均等法改正案7条では、禁止対象(間接差別)を「労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」と定義しながら、これを一般的に禁止するのではなく、「厚生労働省令で定めるもの」に限定して禁止している。しかも、省令で定めるものは、(1)募集・採用における身長・体重・体力要件、(2)コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤要件、(3)昇進における転勤経験要件の3類型に限られるという。これでは、雇用形態の違い(正社員・契約社員・パートほか)を要件としたり、「住民票上の世帯主であること」(平成14.7.3.大阪高裁判決・被災者自立支援金請求事件)を要件とするなど、現存する多くの間接差別が、改正均等法では許されるがごとき印象を与える。
政府は、今回省令で定められる予定の類型外のものについては、「判例の集積を待つ」「公序による制限も考えられる」と説明している。しかし、法令が「禁止すべき措置」を限定列挙する場合、該当しない措置については合法性が推定されるから、省令で定める以外の間接差別を訴訟で争うことは、法改正前よりむしろ困難となるおそれがある。一方、間接差別の外形を有する措置も、事業主が「合理的な理由」を証明すれば、違法な差別とはされないから(改正案第7条後段)、禁止対象を限定しなくても事業主の正当な利益が害されるおそれはなく、何が禁止の対象となるかについては、「指針」(10条)で例示列挙する方法により、適切な対処が可能である。
よって、法律案7条の条文から、「・・・として法律で定めるもの」という文言を削除して、「省令」による限定列挙をやめ、「指針」(10条)により間接差別となるものを例示列挙する方法をとるべきである。
2.参議院では、改正均等法の目的・理念に「仕事と生活の調和」を明記する必要性についても多くの議論がなされたが、政府は、「仕事と生活の調和」の重要性は認めながらも、均等法とは趣旨が異なるので記載しないという。
しかし、長時間・過密労働や住居の移転を伴う転勤など、男性労働者の仕事と生活の調和を無視した労働の実態が、家庭責任の男女平等分担の促進を妨げ、女性労働者の仕事と生活の調和を一層困難にしている。雇用の場における男女の機会均等の実現は、男女労働者が、ともに「仕事と生活の調和」をはかりつつ働き続けることのできる条件整備なくしては、ありえない。
よって、均等法の目的・理念(1~2条)に「仕事と生活の調和」を明記して、法の解釈・適用のあり方を示すとともに、啓発活動(3条)や基本方針の内容(4条)・調査等の対象(28条)等とすべきである。
3.均等法改正案6条では、均等法の差別的取扱禁止規定の対象として、新たに「降格」等を追加したが、「賃金」は均等法の禁止対象とはされていない。
政府は、賃金差別に関しては、労働基準法に男女同一賃金を定める規定(4条)があるため、重複した規定は不要であると説明する。
しかし、直接差別でも間接差別でも、雇用の場における差別は、結局のところ、その殆どが「賃金」の格差として収斂される。均等法の差別取扱の禁止対象に「賃金」を加えることで、均等法特有の諸規定、例えば、「間接差別」(改正7条)、「紛争当事者に対する援助」(11条以下。助言・指導・勧告・調停等。)「事業主に対する措置」(25条以下。報告の徴収・助言・指導・勧告・公表等。)等を、賃金についても利用することができるようになる効果がある。
よって、「賃金」についても、均等法の差別禁止対象に加えるべきである。
4.なお、参議院では、「5年経過後の見直し」を付加する修正がなされたが、めまぐるしく変化する現代にあっては、その見直しの頻度も、せめて2年程度とすべきである。また、参議院厚生労働委員会では、その議論をもとに、ポジティブアクション(積極的是正措置)の一層の普及推進等を含む7項目の付帯決議がなされたが、衆議院においては、これらにも留意し、より充実した論議がなされ、よりよい改正がなされることを望むものである。
2006(平成18)年 5月18日
滋賀弁護士会 会長 羽座岡広宣